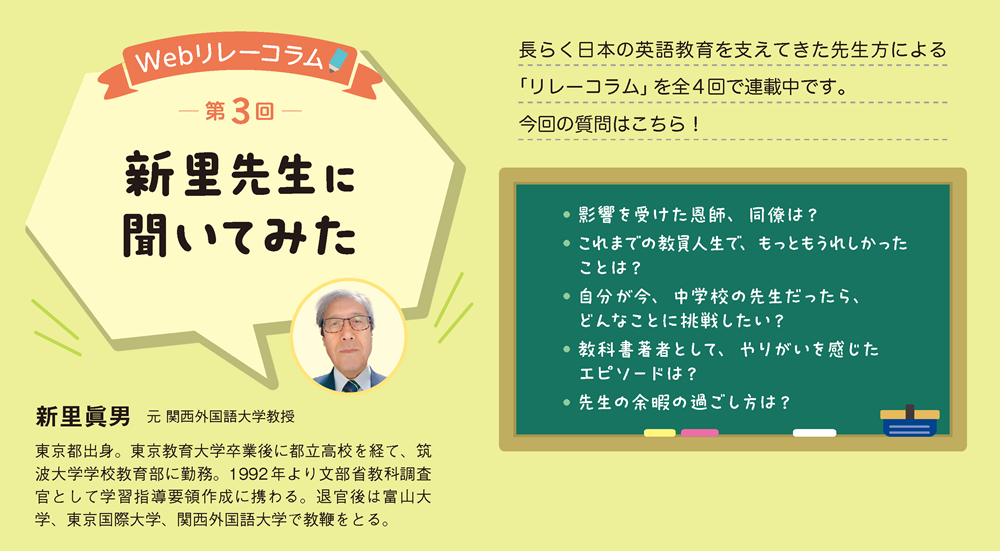|
影響を受けた恩師、同僚は? |
 |
新設の都立高等学校に新卒教師として採用されてから5年経ったとき、大学の恩師から東京教育大学附属高等学校(現在の筑波大学附属高等学校/以下、附高)に行くようにと言われた。教育実習ではあえて避けていたので断りたかったが、それは許されないことだった。 附高といえば、H. E. PalmerのOral Methodの「本拠地」である。しかし、転勤して2か月が経っても、文法訳読式の授業しかできなかった。 そんな状態で悶々としていたある日、体育館の倉庫で部活の片付けをしていると、私の授業を受けていた1人の生徒と先輩卒業生が話しているのを扉の陰から聞いた。 先輩:今度来た新しい英語の先生はどう? 新里先生だっけ? 生徒:読んで訳して、訳して読んでの授業です。ひどいですよ。 このやり取りを盗み聞いて、やっと火がついた。同僚の先生に授業を見せていただいたりして、Oral Methodの授業のやり方を少しずつ取り入れていった。 とりわけ辛かったのは、新教材のOral Introductionだった。教科書の本文を簡単な英語に言い換え、生徒とやり取りをしながら、内容導入する方法である。元来、英語を読むことは好きだったが、自分の思いを英語で表現する経験がほとんどなかったので、非常に苦労した。Oral Introductionの原稿を作成し、それを完璧に覚えて授業に出る。そのためには、1時間の授業のためにその3倍の時間が必要だった。それでも足りず、通勤電車の中でも声に出さずくり返し練習した。そんな毎日に慣れるのに、数年はかかった。もちろん、同僚の先生方からもいろいろご教示いただいた。 しかし、思えば、あの時、私の授業を酷評した生徒こそ、私の英語教師としてのいちばん大きな「恩人」だったかもしれない。 |
 |
これまでの教員人生で、もっともうれしかったことは? |
 |
附高に移って3年目、オーストラリア政府の奨学金を得て、キャンベラ大学(当時の名称は Canberra College of Advanced Education)に約1年間留学した。はじめのうちは、Aussie Englishの独特の発音に戸惑ったが、慣れてくるとその人懐っこい発音が心地よくなった。そんな経験を与えてくれた附高に今でも感謝している。 もう1つうれしかったことがある。同僚の齋藤誠毅先生に誘われて、語学教育研究所(以下、語研)の研究員になったことである。語研といえば、H.E. Palmerが設立し、初代の所長を務めた団体である。彼の指導理論を実践しているのが附高であった。当時の私は、オーストラリアから帰国後、一層Palmer Methodに興味を抱き、都内にあるBritish Councilの図書館に行き、Palmerの著書を次々に借りて読んでいた。しかし、一人で読み進めることは、非常に苦痛・重荷であると感じていたところだった。 語研に入り、Palmerの著作を他の若手研究員と読み合わせしながら、Palmerの考え方を自分たちの授業でどう生かせるかを考えることは、至上の楽しみであり、実のある経験だった。 その後、自分でも少しは授業技術が向上したかなと感じ始めた1987年に語研大会(於学習院大学)の舞台で500名以上(?)の参加者の前で生の授業をした。その日、名誉あるPalmer賞をいただいたが、もし授業が失敗していたら、と思うと、今でも心臓が潰れそうになる。 |
 |
自分が今、中学校の先生だったら、どんなことに挑戦したい? |
 |
私が高校の英語教師だったときは、とにかく生徒に英語で話しかけ、説明し、質問することを中心にした授業を行っていた。そのため、自分の英語の発音や声の大きさ、スピード等に注意しながら、教科書の英語をいかに彼らに理解しやすいレベルで話しかけるかに重点を置いていた。 しかし、中学校の授業を多く拝見することになってからはむしろ、教師がたくさん生徒に語りかけ、英語に触れさせるかということより、生徒一人ひとりにいかに自分の生活や経験、思いなどを英語で表現させるかということのほうが大切ではないかと思うようになった。 理由は、言語は自分で使ってみて初めて身につけることができると実感したからである。43歳で文部省(当時)の教科調査官になり、さまざまな場所で英語のスピーチをしたり、英語で先生方と議論したりしたが、最初の頃はかなりくわしい原稿を事前に用意しなくては話せなかった。しかし場数を踏むうちに、ある程度内容の方向性を事前に考えておくだけで、かなり自然に英語が使えるようになった。 中学生にとっても同じプロセスが大切ではないか。教師による適切な英語での語りはもちろん大切である。しかし、生徒が自分の生活体験や思いを少し深く考え、それを生徒どうしが英語で伝え合ったり、お互いに質問し合ったり、時には教師に質問をするような展開がもっともっとあってもよいのではないか。 ある先生が「生徒たちには『相手意識』をもって英語を使う機会を与えたい」と言っていた。それも大事だが、私は生徒にはもっと「自分意識」(私はこう考える)をもって英語を使わせたいと思う。教科書内容の単なる“retelling”ではなく、“English to express your own ideas”に重点を置いた授業の実現を願っている。 |
 |
教科書著者として、やりがいを感じたエピソードは? |
 |
中学校SUNSHINEの編集作業の過程でいちばん感銘を受けたのは、教科書編者になった中・高・大の英語教師がそれぞれの興味・関心に基づいてさまざまなテーマの題材を持ち寄ったことである。それも、それぞれの題材が単におもしろいというだけではなく、中学生にぜひ考えてもらい、知ってもらい、味わってもらいたいという強い思いが込められていた。そんな思いを持った先生方が集まって始まったSUNSHINEの編集会議は、非常に「熱い」ものだった。 例えば、SUNSHINE 2にあるReading 教材では、1890年に和歌山県沖で海難事故に遭ったトルコ船が、地元の村民の助けにより、無事に帰還した話を取り上げている。私自身それまで全く知らなかった歴史である。そのほぼ100年後の1985年、イラン・イラク戦争の真っ最中に、トルコ政府の救援機が日本人215名全員を乗せてテヘラン空港を脱出した。さらに、1999年のトルコ大地震のときは日本から、そして、2011年の東日本大震災のときにはトルコから救援隊が派遣された。このように、100年以上前の出来事をきっかけに、日本国民とトルコ国民は恩を送り合っているのだ。これらの事実がSUNSHINEの教科書には淡々とした英文で語られている。この歴史を読んで感動しない生徒がいるだろうか。私自身は「ああ、教科書編集に関わることで、こんな感動が得られるのか、生徒にも同じ感動を味わってほしい」と感じていた。私が中学で教えることができたら、生徒に“The villagers in Wakayama helped the foreigners. Can you do the same thing to foreigners today?”とか、“The Turkish airplane came to Iran to save the Japanese people. What do you think of this relationship between Turkey and Japan?”などと質問し、生徒に自分の思いを英語で表現してもらいたい。感動的なストーリーこそ、そのような自己表現活動にふさわしいのではないか。3年のFaithful ElephantsやMalala’s Voice for the Futureも同様に扱いたい。そのように言えることが私にとっての幸せである。 |
 |
先生の余暇の過ごし方は? |
 |
関西外国語大学を2年前に退職して、私の英語教師生活は終了した。英語を教えることはなくなったが、自分ではまだまだ英語力が足りないと思っている。 大学時代にアメリカ文学を専攻していたので、今でもアメリカの探偵小説や恋愛小説を読んでいる。しかし、英語でのコミュニケーション能力を少しでも高めたいと思う気持ちがあり、住んでいる市の英語サークルに入り、いろいろなテーマについて英語で議論をしている。 たとえば先週は、さまざまな国々で今年度に行われる国政レベルの選挙というテーマを扱った。情報を当番の人が英語でまとめ、ネイティブの先生に英語表現について訂正やコメントをしていただいたあとで、10名のメンバーが英語で議論をした。 ほぼ全員が私と同世代であるが、かつては化学者だった人、会社から派遣されてニューヨークで6年間過ごした人、その他英語圏だけでなく、いろいろな国々で仕事をしてきた人たちである。それぞれの英語表現力は非常に高く、私もうかうかしていられない。 この会は土曜日の10時から2時間行われるが、その準備に私は5~6時間をかけている。それだけ緊張し、つらい会であるが、自分の英語力を維持し、さらに伸ばすためには、これほどよい機会はないと思っている。ネイティブの先生から学ぶことは当然多いが、他のメンバーが使う英語表現や学習態度から学べることも多い。会の終了後はいつも「次回も頑張るぞ」と、学習意欲をかき立てられている。 その他、PC上でLuke’s English Podcast を聞いたり、朝日新聞の英語版を読んだり、Youtubeを使って4畳半の書斎で1人で歌ったりすることも私の余暇の過ごし方であり、同時にストレス解消法?でもある。これからも、体力と家庭の事情が許す限り、頑張りたいと思う。 |
| もどる | 第2回へ | 第4回へ |