
Q. 北斎は「冨嶽三十六景」をはじめとする多くの浮世絵を残していますが、そもそも浮世絵にはどんな特徴があるのですか?
浮世絵は大きく分けて肉筆画と木版画の2種類があり、それぞれに特徴があります。肉筆画は、力強いものから繊細なものまであり、多彩な描線の表現や色彩の濃淡など、絵師の直接的な筆づかいによる表現が特徴です。浮世絵版画は、ぼかし摺り、薄墨、金銀摺り、空摺りなど、版画ならではの摺りの技法による表現が特徴です。さらに木版画は、肉筆画と違い大量に生産することができることも特徴の一つです。

ここでは、造形ジャーナル448号で紹介した「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」に関連して、「浮世絵」のお話を千葉さんにお聞きします!


Q. 北斎は「冨嶽三十六景」をはじめとする多くの浮世絵を残していますが、そもそも浮世絵にはどんな特徴があるのですか?
浮世絵は大きく分けて肉筆画と木版画の2種類があり、それぞれに特徴があります。肉筆画は、力強いものから繊細なものまであり、多彩な描線の表現や色彩の濃淡など、絵師の直接的な筆づかいによる表現が特徴です。浮世絵版画は、ぼかし摺り、薄墨、金銀摺り、空摺りなど、版画ならではの摺りの技法による表現が特徴です。さらに木版画は、肉筆画と違い大量に生産することができることも特徴の一つです。

Q. 当時、浮世絵はどのような人々に人気があったのですか?
作品に描かれているモチーフや内容などが、庶民にとって身近で理解しやすいものであったため、浮世絵版画は多くの庶民にも親しまれていました。時期や仕様によって異なりますが、例えば「冨嶽三十六景」と同じ大判の作品は、現在の価格で1000円以下で購入できたため、庶民も手に取りやすいものだったと考えられます。
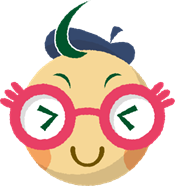
Q. 庶民にとっても身近な芸術作品だったんですね! 当時はどのようなところで購入することができたのですか?
主に版元が営む絵草紙屋(現在の書店のような店舗)で販売されていました。また、地方の人々が江戸を訪れた際に、お土産として浮世絵版画を購入することもあり、浮世絵は広く普及していきました。

Q. 浮世絵版画は、社会の中で何か役割を担っていたのですか?
現在は芸術作品として評価されていますが、当時は日常生活に密着したものであり、その役割も多岐にわたっていました。人々をたのしませる娯楽的要素もあれば、かわら版のような報道的・広報的要素を担うものもありました。浮世絵が広く普及する中で、風刺的な意味をもつものも出回り、時には政策の意向に反するとして浮世絵の内容に関して規制がかけられることもありました。

Q. 浮世絵は当時の人々の生活にとても身近な存在だったのですね。最後に、「冨嶽三十六景」はどのような理由で制作されたのか、ぜひ知りたいです!
「冨嶽三十六景」は版元である西村屋与八の依頼で制作されました。当時、富士講とよばれる富士山を神聖なものとする信仰が流行していました。「冨嶽三十六景」はこの富士講の流行に合わせて企画されたもので、版元から絵師である葛飾北斎に依頼したと考えられています。

「冨嶽三十六景」の制作にはそんな背景があったのですね! 今回のインタビューで、浮世絵についてもたくさん知ることができました。千葉さん、どうもありがとうございました!